北海道札幌英藍高等学校

北海道札幌英藍高等学校
郷土研究部8月の活動は夏休み中の8月7日(水)に「札幌市中心部文化施設巡検」として、札幌テレビ塔・札幌市時計台・大通美術館を見学しました。夏休み中ということもあり、少し遠い場所へ行く計画もありましたが、今年は石狩出身の部員も多く意外と札幌の中心を知らないということもあり、今回の企画となりました。3年次生2名、2年次生2名、1年次生3名、顧問の菊池教諭の計8名での活動となりました。
地下鉄大通駅ポールタウン前に集合し、最初に札幌テレビ塔へ向かいました。





当日は朝から暑く、また観光名所ということで観光客がすでにごった返している状態でした。エレベーターで上まで上がり、札幌市内の様子や遠くは英藍高校の近辺や石狩湾方面まで見ることができqqました。また北大や大倉山ジャンプ台など、今後訪れるであろう場所も眺めることができました。


テレビ塔の次は近接する札幌市時計台へ行きました。こちらも札幌を代表する文化施設で、たくさんの観光客であふれていました。こちらはすでに学んできた札幌農学校(や北海道大学)との関わりが深い施設で、生徒たちは展示されているものとこれまで見学してきたことをリンクさせるような形で、学びを深めていました。




時計台の次は大通美術館へ向かいました。こちらは「ギャラリー大通美術館」という名前も付いていて、常設の展示があるわけではなく、アーティストが在廊して自分の作品を紹介する、というスタイルの施設でした。今回は栗山町在住の「木の工房るか」さん、札幌在住の仲良し女子二人組「mink」さんと「宮の宮」さんの作品が展示されていました。特に「mink」さんと「宮の宮」さんは生徒たちと年齢が近いこともあり、作品を通じてとても話が盛り上がっていました。また木の温もりを感じる「木の工房るか」さんの作品にも、生徒たちは興味津々でした。普通の美術館を見学するのとはひと味違った雰囲気で、生徒たちには貴重な体験となりました。







最後に美術館の出口そばにあった、美唄市出身・イタリア在住彫刻家の安田侃さんの大理石作品を囲みながらミーティングをしました。


生徒たちは、以下のような感想を述べていました。
・テレビ塔では札幌の中心部を見渡すことができて、札幌市資料館など以前行った所も見えて感慨深かった。
・初めてテレビ塔に上ったが、中の展示と上からの風景で札幌の歴史に触れることができた。
・時計台は以前来たときよりも、観光客が増えている印象だった。
・昔は演舞場や体育館、今はコンサート会場にもなっていて、長きに渡って人々に親しまれていることを知ることができた。
・時計台に初めて来たが、時計台を題材にした曲(音楽)がたくさんあること、昔の時計台の部品が展示されていたことに興味をひかれた。
・大通美術館では在廊していた作者さんと作品について話し合うなど、得がたい経験を得られた。
・素晴らしい絵がたくさんあって、お金があれば買いたかった。
・中学校では美術部だったので、プロの絵を見ることが出来て勉強になった。
9月は中島公園で、豊平館見学・Kitaraホールでの札響演奏会鑑賞の予定です。
郷土研究部7月の活動は、学校祭後の振替休業日の7月9日(火)にサケのふるさと千歳水族館の見学に行きました。今回は本校新聞局が部活動の取材ということで同行しました。残念ながら郷土研究部員で都合が合わず参加できない生徒が多かったのですが、郷土研究部員3名、新聞局員5名、顧問の菊池教諭の合計9名での活動となりました。
JR札幌駅北口に集合し、千歳駅から徒歩でサケのふるさと千歳水族館へ向かいました。




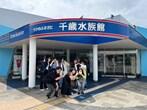
こちらの水族館はコロナの時期に来たことがありましたが、今のメンバーで来るのは初めてで、隣に併設されている道の駅がリニューアルされていることもあり、新鮮な気分を感じました。近所の保育園の子供たちや家族連れが来ていて、平日にしては意外と人が多い印象でした。
サケのふるさと千歳水族館について、ホームページから以下の説明を紹介します。
⇒「サケのふるさと千歳水族館は、淡水では日本最大級の水槽を有する水族館で、館内ではサケの仲間や北海道の淡水魚を中心に、世界各地の様々な淡水生物を観察することができます。」
⇒「千歳川の水中を直接見ることのできる日本初の施設「水中観察ゾーン」では、四季折々の千歳川の生き物たちの営みを間近に観察することができます。中でも、秋に産卵のため川をさかのぼるサケの群れは必見です。サケの稚魚放流体験などのイベントや企画展なども数多く開催しています。」
生徒たちはサケだけでなく、様々な魚や水辺の生き物を間近に見て・触れて(ドクターフィッシュに手の角質を食べてもらっていました!!)、教科書からだけでは学べない貴重な体験が出来ました。











見学の後半では、アイヌ人と北海道開拓期の日本人とのサケ漁の違いや、アイヌや全国のサケ料理の比較など、今まで学んできたことと比較できるような展示も見ることが出来て、大変勉強になりました。
生徒たちは以下のような感想を述べていました。
・サケの一生、産卵、歴史、料理法、アイヌについてなど、幅広い資料が多くて学びが多かった。
・サケ以外にもいろいろな魚を見れた。特に電気ウナギとスティングレー(エイ)が印象的だった。
・千歳川の中のサケを直接見られる展示は、とても見応えがあった。
・新聞局との合同活動だったが、細かく取材を受けるみたいな堅苦しいものではなく、意見や感想を交わすような感じで、楽しく交流できた。また一緒に活動したいと思った。
・今後も新聞局とポスターや新聞の作成で、互いに協力しながら高め合えたらいいと思った。
8月は札幌市内中心部の施設を回る予定です。
7月5日(金)・6日(土)の学校祭で、郷土研究部は例年同様、社会科教室にて活動内容にかかわる展示を行いました。活動毎に作っているポスター(昨年度と今年度の分の一部)を展示し、また過去の活動をパソコンのスライドに簡単にまとめたものをテレビで放映しました。



来場者アンケートでは、以下のような感想をいただきました。
・ポスターで活動を発信してくれているのは嬉しいです。エドウィン・ダン記念館は行ってみたいと思っていたので、紹介を見られてよかったです。
・部員さんの説明も分かりやすく、地域に対する愛が伝わってきました。
・同じ場所にもう一度行く、というのがすごくいいと思いました。行く時の年齢や季節が違うと見え方や感じ方が変わるので、新しい発見もあると思います。
・地元を知れるいい機会でした。ポスターがすごく分かりやすかった。頑張ってください!!
部員達には大変励みになりました。これからも活動の発信を続けますので、応援や感想をよろしくお願いします。
今月の活動は、6月9日(日)に北大祭と北大博物館へ行きました。当初は別の場所を計画していましたが、昨年の北大祭でのIFF(International Food Festival )の様子を先輩方から聞いた1年次生が、ぜひ行きたいと希望し、昨年と同じ形になりました。今回は3年次生2名、1年次生4名、体験入部の2年次生1名、顧問の菊池・武藤両教諭の合計9名での活動となりました。
JR札幌駅北口に集合し、北大へ向かいました。

正門から入場してクラーク像を確認した後、メインストリートを農学部付近から北方向へ向かいました。(農学部の熊に関するブースは最近の話題のニュースと大いに関係がありました。)特にお目当てにしていたIFFは留学生たちによるエスニックフードの出店で、主にアジア・アフリカの料理でした。生徒たちは外国人留学生にも何とか話しかけながら(!?)、各国の食文化を楽しんでいました。IFFを抜けると留学生ではない(!?)北大生たちによる様々な模擬店もあり、中には湧別高校生徒が協力する湧別町のブース、北大生が地域創生で関わっている津別町のブースなど興味深い出店もありました。

北大祭で食文化を堪能した後は、北大博物館を見学しました。1年次生にとっては初めての訪問で、1階は北海道開拓と北大の歴史、2階以上は各学部の研究成果を分かりやすく展示したものが中心で、生徒たちは各々が興味あるものを熱心に見学していました。



生徒たちは以下のような感想を述べていました。
・IFFは何となくカレー系が多いように感じた。北大祭はさすが大学生の企画力なのか、良い意味で普通の大きなお祭りだった。
・昨年同様たくさんの屋台があり、見応えがあった。北大の学生さんともいろいろお話ができて、視野が広がった。
・IFFの出店の工夫を見て、自分たちの学校祭にも生かせると思った。また各国の料理が見たことのないものが多くて楽しかった。
・外国の方と少しだけだったけど会話ができて良かった。
・北大祭はお堅いお祭り、と勝手に想像していたけど実際にはいろいろな世代の人たちがたくさん来て楽しんでいて驚いた。
・外国の料理について、食材をどこから手に入れているのかに興味がわいた。
・北大博物館に初めて来たが、いろいろな世界を味わえて良かった。
・3回目の北大博物館訪問だったが、展示だけでなく自分の見方が変化したことも感じ、新鮮な気持ちで見ることができた。
・宇宙の展示が気になり、もっと見たくなりました。
・恐竜の化石の展示に一番興味を持った。授業で学んだことも出ていて、さらに理解が深まった。
・北大博物館の中は外のお祭りの雰囲気とは真逆のとても真面目な内容で、動物の剥製や昆虫の標本が特に心に残った。
来月はサケのふるさと千歳水族館を見学する予定です。
今月の活動は、5月18日(土)に札幌市資料館と北大植物園へ行きました。両施設とも札幌の中心部にあり駅からアクセスしやすく、札幌の歴史と自然を同時に学べる良い機会となりました。今回は3年次生1名、2年次生2名、1年次生4名、顧問の菊池教諭の合計8名での活動となりました。
地下鉄大通駅に集合し、大通公園の中を通りながら札幌市資料館へ向かいました。


ライラック祭りやラーメン・フェスの準備をしている中を通過していきましたが、途中で北海道開拓に尽力したエドウィン・ダンと黒田清隆の像前で記念撮影をしました。昨年春にエドウィン・ダン記念館へ行った時のことを思い出した部員もいました。
大通公園の最も西側に位置する札幌市資料館の前には庭園があり、札幌の姉妹都市瀋陽(中国)とのつながりを表す獅子像や、美しい植物がたくさんありました。


札幌市資料館は大正15年(1926年)に札幌控訴院(今日の高等裁判所に相当)として誕生した建物が、現在は資料館として市民に開かれた施設となっていて、令和2年(2020年)に国の重要文化財に指定されました。


内部は刑事法廷展示室やまちの歴史展示室、貸しギャラリーなどがあり、当時の裁判の様子を体験したり、札幌の発展の歴史を学んだりできる興味深いものでした。茨城県の中学生が修学旅行の自主研修に来ている場面にも遭遇し、生徒たちは価値ある施設であることを実感していました。






札幌市資料館見学後は、徒歩15分ほどで北大植物園に到着しました。北大植物園の歴史は明治10年(1877年)、札幌農学校教頭だったクラーク博士の進言に始まり、後に初代園長となる宮部金吾氏の計画・設計で明治19年(1886年)に開園しました。(日本で2番目に古い植物園だそうです。)様々な植物に恵まれているだけでなく、北方民族資料室には貴重なアイヌ・ウィルタ民族の生活資料が、博物館には南極観測で活躍した樺太犬タロや世界唯一のエゾオオカミの剝製など、大変貴重な資料があり、郷土研究部として学ぶものの宝庫でした。生徒たちは博物館も植物園内も、大変興味深く見学していました。







生徒たちは以下のような感想を述べていました。
・札幌市資料館の交通や札幌軟石の展示について、今まで訪問した施設や篠路の歴史とリンクする部分も多く、知識をより吸収できた。
・昔は書記など、裁判官以外の人も法服や帽子を身に着けていたことを初めて知った。
・裁判所のテーミス像を後から調べたら、ヨーロッパでは正義の象徴として街中でも見ることができることが分かった。
・札幌の様々な地名の由来や歴史を知ることができて、札幌についての知識が深まった。
・北大植物園の博物館に展示されていた、宮部金吾氏の内村鑑三氏・新渡戸稲造氏と英語でやり取りした手紙や、漢文で書かれた儀式の式辞に驚いた。
・エドウィン・ダン記念館で見たオオカミ絶滅の話や、北大博物館で見たのと同じような英語のノートがあり、これらのことを部活のポスターを通してもっといろいろな人に知ってもらえるよう頑張りたいと思った。
・アイヌ民族について、今までは日本から見た情報しか知らなかったので、他の国ではどんな風に考えられているのかにも興味を持った。
・開拓以前の札幌の植生を知ることができた。またアイヌの熊送りの動画は大変興味深かった。
・博物館内の動物の剥製や、瓶内にホルマリン漬けになった蛙・蛇・トカゲなどがとても印象的だった。
・一年生全員が参加しての活動は今回が初めてだったが、前回同様仲良くできて、日常のポスター作成作業で交流が上手くできているからだと感じた。
来月の活動は、北大祭の外国人留学生によるエスニックフードコートと、北大博物館の見学を予定しています。
また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。
教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf